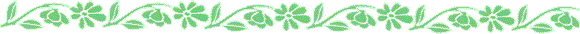 |
FILE68 ケイリュウタチツボスミレ
Viola grypoceras A.Grey var. ripensis
N.Yamada et Okamoto |
 |
| 図1 ケイリュウタチツボスミレの株 穏やかな紫色の花が美しい |
|
 |
 |
| 図3 比較画像 タチツボスミレの花 |
|
 |
| 図4 比較画像 タチツボスミレの葉 |
|
|
| 図2 岩の隙間で大株となる。葉の基部は浅い心形。 |
|
|
 |
図5 穏やかな紫色の花がほとんどだが、時には濃いめの紫花もある。(2003年4月16日)
|
 |
 |
| 図6 葉(浅い心形ないし切形) |
図7 花の側面 |
 |
 |
| 図8 節間の詰まった太い地下茎と葉と花。地下茎が露出しているのは、増水したときに洗い出されてしまったから。 |
図9 托葉 |
|
 |
| 図10 ユキヤナギ 川岸の岩場はユキヤナギの好適地 |
|
|
 |
図11 川原から2〜3mの高さまでのところまで生育するユキヤナギ(岩盤の上の緑の部分の中に斑点状に見える白い部分がユキヤナギの花)
|
 |
| 図12 花のあとの茎葉は長三角形や、基部がくさび形の菱形に近い型になる。(2001年7月22日) |
|
 |
| 図13 同じく夏葉。(2001年8月13日) |
|
最近認識されたタチツボスミレの渓流型変種です。
石川県では、加賀の手取川中流域の岩石がごろごろした川原や岩上にあります。面白いことに、水面から3m程の高さのところまでの岩と川原の砂の境目や岩の割れ目にだけ生育し、それより上のところには、全く見られません。
このあたりはちょうど、ユキヤナギ(図10)の自生地でもあります。ユキヤナギは川岸に帯のように分布しており(図11)、このあたりがおそらく増水した時、冠水する範囲だと思われます。
タチツボスミレとの区別点は、「日本のスミレ」(いがりまさし著)によれば、
1 増水すると冠水するような河川中流域の岩石の隙間や川原に生育。
2 花弁が細い傾向がある。
3 根生葉の基部がタチツボスミレのような深い心形にならない
4 葉に光沢がある。
5 地下茎が良く発達する。
6 花の後の茎葉は長三角形や、基部がくさび形の菱形に近い型になる。
とされています。
渓流沿い植物 (rheophyte)の定義:1999. 加藤雅啓. 植物の進化形態学.
p139. 東京大学出版会. よりの引用。
渓流沿い植物は van Steenis (1981, 1987)
によると、「自然界では急流の渓流や河川の川床(および川岸)に限定され、洪水の上限まで生育するが、周期的に起こる洪水の到達水位をこえて生育することはない植物の種である」と定義される。
|
ケイリュウタチツボスミレはその名のごとく、渓流域に生育する「渓流沿い植物」の一種です。
タチツボスミレとの区別は微妙なのですが、慣れてくると多分こうだろうとの識別ができます。そのときの最初のポイントは「葉の光沢」です。それは、水流や水流に乗って流れてくる砂粒やゴミのようなものから表皮を守るためにクチクラ層が厚くなっているためだと考えられています(図6)。
また、夏葉(花の後の茎葉)が長三角形や、基部がくさび形の菱形に近い型になる、のも重要な特徴です(図12・13)。このような型になるのは、水流を受け流すためだろうと考えられます。
この川の同じ場所に生育するユキヤナギ、ネコヤナギ、サツキも、流線型のスマートな葉をしており、おそらく渓流沿い植物と呼んで良いものでしょう。
渓流域の岩の割れ目など普段は乾燥にさらされる場所に生育しながら、大雨による増水で冠水するという極悪な環境に良く耐えている健気なスミレです。確かに生育場所は増水したときに冠水するような場所ですが、果たして現実はどうか?ということが気になっていました。
|
 |
| 図14 この川で最初に発見したケイリュウタチツボスミレ。大岩の根元の岩隙に生育。 |
 |
| 図15 最初にケイリュウタチツボスミレを発見した大岩(画像左)の根元は、完全に水没。(2003年4月22日) |
ちょうど今年(2003年)4月19〜21日は雨が降り続きました。増水しているはずです。しかし、増水している時はとても危険な渓流域なので近づくのは遠慮していました。
4月22日、晴天です。休暇が取れたので、出かけました。普段よりは増水していましたが、かなり水は引いていました。図14の大岩の根元は、初めてケイリュウタチツボスミレを見つけた場所ですが、完全に水没しています(図15)。普段は、河床を伝って自由に歩けるのですが今日はそれが不可能でした。何度も崖を登ったり降りたりしながら心当たりの場所を探して歩きました。
ついに、増水した水に洗われているケイリュウタチツボスミレを見つけました(図16)。(水没したものは撮影不可能でした。)。
図17は、水流で地下茎(3本)が洗い出されてしまったものです。岩隙に入った部分でかろうじて保持されている状態でぐらぐらでした。
この上にも沢山咲いていましたが、増水したときに洗われた様子が見て取れました。
|
 |
| 図16 増水した水に洗われるケイリュウタチツボスミレ (2003年4月22日) |
|
 |
| 図17 少し見えにくいが、水流のせいで、地下茎がすっかり洗い出されてしまった。わずかに岩隙に入った部分で支えられている。(2003年4月22日) |
正確な測量ではありませんが、この撮影場所は普段の水面から言えばおそらく1mの所です。この上更に1m位の所までが今回冠水したようです。その更に1mほど上の所の木の枝にゴミが引っかかっていますので、大荒れの時はそこまで、すなわち、普段の水面より少なくとも3mは冠水することがあると考えられます。
|
|
|
|
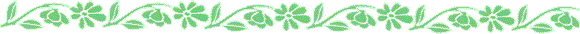 |